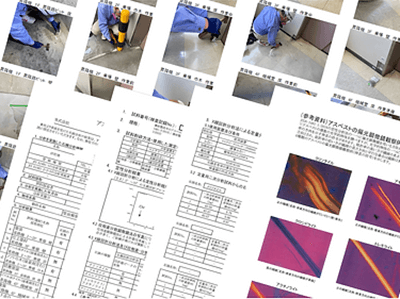分析方法は次の通りです。
| 規格番号 | 分析タイプ | 主な使用機器 | 特徴 |
| JIS A 1481-1 | 定性(有無)分析 | 実体顕微鏡 偏光顕微鏡 | ISO 22262-1準拠 層別分析可能 分析者の力量依存度高い |
| JIS A 1481-2 | 定性(有無)分析 | X線回折装置 位相差分散顕微鏡 | 日本独自の方法 分析者の力量依存度低い |
| JIS A 1481-3 | 定量(含有率)分析 | X線回折装置 | - |
| JIS A 1481-4 | 定量(含有率)分析 | 実体顕微鏡 偏光顕微鏡 | ISO 22262-2準拠 |
| JIS A 1481-5 | 定量(含有率)分析 | X線回折装置 | ISO 22262-3準拠 |
JIS A 1481-1を採用する分析者が最も多く、JIS A 1481-1、-2を併用する分析者もいます。
通常は国際標準準拠のJIS A 1481-1を指定しています。
法は定量(含有率)分析を求めていないため、JIS A 1481-3、-4、-5は指定しません。
JIS A 1481-1 アスベスト分析作業手順書は次の通りです。
1. 試料の受け取りと観察
・試料を受け取る
・肉眼で全体を観察し、色や材質を記録する
2. 試料の前処理
必要に応じて以下の処理を行う
・灰化(カイカ):485℃で10時間加熱し、有機繊維を除去
・酸処理:2mol/Lの塩酸で攪拌し、多くの成分を除去
・沈殿性および浮遊性:水中での沈降や浮遊により不要成分を除去
3. 実体顕微鏡による観察
・試料全体を実体顕微鏡で観察
・繊維の有無を確認し、ある場合は仮同定を行う
・層状の試料の場合、全ての層について観察する
4. プレパラートの作製
・観察された繊維について、偏光顕微鏡用のプレパラートを作製する
5. 偏光顕微鏡による同定
以下の6つの光学的特性を確認し、繊維を同定する
・形態
・色及び多色性
・複屈折
・消光角
・伸長の符号
・屈折率
6. アスベスト含有の判定
・観察結果に基づき、アスベストの含有の有無を判定する
7. 結果の報告
・分析結果をまとめ、報告書を作成する