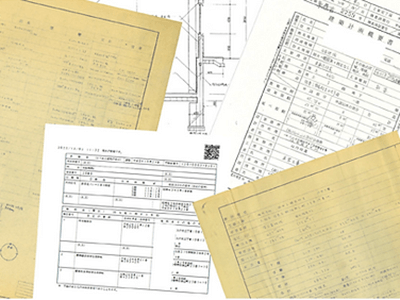
的確で効率的な調査の鍵は調査計画です。調査計画の質は情報量に比例します。お客様へのインタビュー、竣工図等の設計図書、確認済証、登記記録、石綿建材データベース等から情報を収集します。
書面調査により目視調査が確実・迅速に実施できます。場合によっては、目視調査以降の調査が不要になることもあります。
正確性、迅速性・コスパの観点から、書面調査は石綿事前調査の最も重要な作業です。
書面調査の手順
- 工事の範囲と作業内容を確認します。
- 過去の全ての工事の建築概要、仕上表、平面図、立面図、展開図等を確認します。
- 過去の全ての石綿調査結果を確認します。
- お客様に書面以外の情報を確認します。
- 棟・階・部屋・部位毎の建材のリストを作成します。
- 過去の石綿調査の時期と結果をリストに記載します。
- 建材毎に石綿含有建材が製造された期間をリストに記載します。
- 過去の全ての工事の着手年と石綿含有建材製造期間から石綿含有疑義建材をチェックします。
- 工事対象範囲の石綿含有疑義建材について、同一建材毎の使用面積の概算を算出します。
- 石綿含有疑義建材について、判定方法を総合的に仮定します。
石綿徹底マニュアル 付録Ⅰ 事前調査の方法に沿って調査を記録した石綿事前調査書が元請の義務履行のエビデンスです。
事前調査の第1段階は書面による調査(設計図書等の調査)(以下「書面調査」という。)である。
書面調査では、
①図面などの書面や聞き取りから情報をできる限り入手し(発注者や過去の経緯をよく知る施設管理者や工事業者等の関係者に対するヒアリング等により情報を入手する)
②それらの情報からできる限り多く、石綿の使用の有無に関係する情報を読み取り(工事概要や建築物等に関する情報のほか、建築物等に使用されている個々の建材を把握するとともに、得られた情報から石綿含有の有無の仮判定を行う)
③現地での目視による調査(以下「現地での目視調査」という。)を効率的・効果的に実施できるよう準備を行う(得られた情報を参照しやすいよう整理する)。
書面調査は、調査対象建築物に係る情報を理解・把握することにより、
ⅰ現地での目視調査の効率性を高めるとともに、
ⅱ石綿含有建材の把握漏れ防止につながるなど、
調査の質も高めるものであり、重要な工程である。
これらの質と効率を高めるには、建築や建材などの知識が重要である。
① 発注者等からの情報の入手
ア 発注者等が保有する資料の提供依頼
発注者等に対し、設計図書、過去の維持管理のための調査記録や改造補修時の記録などの提供を依頼する。発注者は建築や石綿に詳しくないことが多いため、
①ヒアリング相手方として管理担当者など詳しい者を要望したり、
②必要な書面の具体例を挙げたり(例:設計図は「確認申請書」「確認済証」という用語を伝えてみる)
③書面の重要性を説明して理解を求める、などするとよい。
発注者等に提供を依頼する主な図面等の種類は以下のとおり。
(ア)設計図書・竣工図書等
建築施工中に設計内容を変更することが多くあるため、竣工図があるなら竣工図を確認するとよい。また、新築時以外にも、増築、改築、修繕、模様替え、用途変更等の際の図面も入手する。
・意匠図(特記仕様書、内外装仕上表、配置図、平面図(防火区画の確認)、立面図、断面図、天井伏図、平面詳細図、断面詳細図、矩計図、各種詳細図、什器備品関連図)
・構造図
・設備図(各図面に特記仕様書が付いている)
(イ)過去の石綿含有建材の調査記録
(ウ)過去に石綿含有建材を処理(除去、封じ込め、囲い込みなど)した履歴(工法、施工日、部屋名・箇所)
(エ)機械設備の分解、廃棄が解体工事に含まれる場合は、用途等の情報
(オ)吹付け材などの劣化状況の調査情報
イ 発注者等関係者からのヒアリング
発注者等に対し、上記アの資料の提供のほか、以下の事項を確認し、聞き取った内容をメモ等に残す。
(ア)建築物等の用途
上記アの資料により確認できる情報のほか、建築物等がどのような用途であったかを確認する。用途から、必要な性能(耐火性、防音性、断熱性・保温性、等)の情報を得ることができる。また、過去の用途の変遷から過去の改修履歴を、逆に過去の改修履歴から過去の用途の変遷を推測できる。
(イ)事前調査の範囲の確認
事前調査の範囲は、調査後行われる予定の工事の目的・内容に照らし、必要十分なものとなるよう発注者等と十分相談の上、確定する。
(ウ)事前調査の実務上の制約の確認(湿潤・破壊・復旧等)
発注者に対して、事前調査の実施に当たって、
①壁の内部の確認や建材の取り外し、
②点検口のない天井の破壊等、
③粉じん飛散抑制剤の散布の可否、
④分析試料採取のための壁等の破壊の可否、
⑤事前調査のための破壊後の復旧の程度、などについて確認する。
さらに、現地での目視調査の際の建築物等の使用・利用状況を確認し、建築物等が使用中の場合は、調査対象室における使用者・利用者の在室状況及び調査のために入室できる時期等を確認する。
なお、工事対象箇所(壁等の内部を含む)を網羅できない場合は、施工までに再度調査が必要である。
(エ)その他
調査の日時、報告書提出期限、報告書に記載すべき内容の確認を行う。その際、現地での目視調査時の立会人(管理者等)が上記(ア)~(ウ)のヒアリング対象者と異なる場合は、立会人との日程調整等も行う。
② 情報の読み取り・活用
発注者等より入手した設計図書、過去の調査記録、ヒアリング内容等から、次のア~エのとおり情報の読み取り等を行うとともに、オのとおり現地での目視調査の準備を行う。
ア 建築物の概要の把握
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造、階数、耐火建築物・準耐火建築物か否か、部屋数等のフロアの概観、竪穴区画や煙突があるか否かなど、建築物の概要を把握する。また、工事に着工した年月、増築・改築・改修の有無と年月日及び用途変更を伴うものか等を確認する。
イ 個々の建材情報の把握
建築物等に使用されている建材の種類等の確認を行う。参考資料(4)に書面調査で参照する書類と得られる情報について、例を示している。
ウ 過去の石綿含有分析の結果
石綿含有無しの判定として使う場合は、特に次の点を確認する。
・分析の対象とした石綿がクリソタイル等の6種類すべてであること
・石綿の含有なしの判定が0.1%以下の基準でなされていること
・同一と考えられる建材の範囲の判断が適切であること
エ 石綿含有の有無の仮判定
個々の建材の石綿含有の有無の判断には、
ⅰ建材の特定(商品名等)と、
ⅱ当該建材の石綿含有情報との照合、が必要である。
ⅰは上記イのとおりであり、ⅱについては、次の(ア)~(エ)のとおり、データベースやメーカー情報等と照合しつつ、石綿含有の有無の仮判定(想定)を行う。
(ア)建材の製造時期や材質による判定
石綿の製造・使用等の禁止(平成18(2006)年9月1日)以降に着工した建築物・工作物(又はその部分)は、原則として石綿含有なしと判断できる。また、例えば、ガラス、金属、木材に石綿が含有していることはないが、これらに石綿が付着していることがあるので注意を要する。
(イ)石綿(アスベスト)含有建材データベースによる判定
国土交通省及び経済産業省が公表しているデータベースは、建材メーカーや加工メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を検索できる。ただし、データベースには、すべての石綿含有建材が掲載されているものではないことから、データベースに存在しないことを以て石綿含有なしの証明にすることはできない。
(ウ)団体・メーカー資料による判定
建材の石綿含有の有無に関するメーカー情報等としては、建材メーカーが自社のウェブサイトにおいて情報を公開していたり、個別の問い合わせに回答していることがある。メーカー証明により石綿含有なしと判断する場合は、
ⅰ無含有証明が対象とする石綿が6種類すべてであるか、
ⅱ無含有証明が対象とする石綿含有率は0.1%以下かについて確認する。
(エ)過去に実施された調査結果による判定
過去に行われた石綿含有建材の調査結果を使用して判定する際の留意事項は以下のとおり。なお、過去に調査された後に、改造、補修された箇所がある場合は、その記録についても確認し、調査対象の建材を確認する。
ⅰ石綿ありの判定
過去に「石綿含有」と判断された建材は、改造、補修で除去された履歴がなければ、石綿ありと判定する。
ⅱ石綿なしの判定
石綿含有なしと判断する場合には、以下の事項に留意して慎重に判定する。
・分析で判定した石綿の種類・含有率(なし判断については含有率が0.1%以下と判定しているか、6種類すべての石綿を対象に分析しているか確認。)
・調査対象建材について同一建材と判断する範囲(裏面情報や採取した試料の結果により、どこまでの建材を同一と判断して石綿含有なしとするか)
・当該過去の調査範囲(具体的な調査範囲について記録がない場合は、調査範囲がわからないため石綿含有なしの判断には直接使えない。)
オ 書面調査結果の整理と現地での目視調査の準備
書面調査で得られた情報については、現地での目視調査において効果的に活用できるよう、整理する必要がある。具体的には、目視調査の作業用資料として、
・現場で、迅速・簡易に情報を記入できるもの
・現場で、調査・判断の流れに沿って記入しやすいもの
・現場で、調査箇所に漏れがないことを確認しやすいもの
となるよう留意しつつ、書面調査で把握できた建材をリストにまとめる。
また、作成した建材のリストや、発注者等関係者からヒアリングした内容をもとに、次のような事項について調査実施計画の策定を行う。
・動線計画(同じタイプの部屋でも改修されていることがあるので、それぞれの部屋を確認する目視調査計画とすることが必要)
・入室可能時間
・特に大きな建築物の場合は、建材確認、裏面表示確認、試料採取などの実施順序・流れ
・発注者との相談予定日時、立会いがない場合の調査当日の連絡先(みなしか、分析かの選択の相談などの確認方法)
